こんにちは、発達障害を持つ双子の娘を育てているゆかりです🍀
発達育児は、毎日が子供との戦いですね…。
その独特なタイミングで起こる、予測不能な癇癪には私自身何度も絶望し、投げ出したくなりました。
今回は、そんな親の悩みのひとつでもある癇癪対応について、私が試した方法や失敗談をお話しします。
________________________________________
発達障害児の親の恐怖のひとつ…。
それは突如として起こる癇癪。
「急に大泣き」「床に寝転んで動かない」など、親も疲れ切ってしまうことがあります。
私自身も何度も途方に暮れましたが、試行錯誤の中で少しラクになった方法があります。
少しでも参考になることがあったら幸いです。
癇癪とは?発達障害の子に多い理由
癇癪とはなぜ起こるか?
周りからは「ただのワガママ」「しつけが悪い」などと見られがちですが、そうではないんですよね。
発達障害の子は元々感情のコントロールが苦手で、言葉で気持ちを表現するのが難しいです。
癇癪とは、気持ちを言葉で伝えられないストレスの爆発
感覚過敏や予定変更などで起こりやすいです。
我が子は見通しの見えないスケジュールでパニックを起こしやすい子でした。
癇癪対応で効果があった3つの方法
① まず安全を確保して“そっと見守る”
そんなこと分かってるわ!!と思う方もいますよね(笑)
癇癪が起きた時は、どうにかして早くおさめようとついあの手この手で構ってしまいがちですが、本人が落ち着くまで見守ることで逆に早く終わることもありました。
見守る際に注意しておくのが、周囲や本人の安全確保です。
危険がないようにだけ注意して落ち着くまで待ちます。
見守る中で見えてくる問題点と改善の一例
・我が家はご近所への迷惑も気になったので窓を閉め切ったり、防音マットを敷いたりの対策をしました。
・私は子供の泣き声が耐えられないタイプなのですが、見守ると決めた時はイヤホンで音楽を聴いたりして、聴覚からのストレスを遮断させた。
子供のことも心配ですが、なるべく自分の精神的負担を減らす対策を取ることで冷静に見守ることができました。
② 言葉ではなく「視覚支援」を使う
- 絵カードや写真で「次にやること」を見せると落ち着きやすかった
これも王道ですが絵カードや写真は本当に使えると思います。
私の場合は、ほとんどスマホで撮影した写真や検索して出した画像を見せて、次にやることだったり、今の状況を伝えていました。
歯医者さんに行くときはそこの診察券も見せたりしました。
その際は、診察券を見せながら「歯医者さん行くよ、歯医者さん」と必ず言葉も添えておくと、いつの間にか「歯医者さん」を認識してくれました。
視覚で得られる情報に加え、リンクしてほしい単語も意識して伝えるようにするとよかったです。
“言葉なんて理解していないよね…”と思っても(私自身がそう思っていた)ぜひ絵カードや写真と一緒に単語だけでも伝えてみてください。 - 私が実行していた簡単スケジュール表?の例
ズボラな私が、キレイにマメにスケジュール管理をして表にまとめていました!
とは口が裂けても言えませんが、ズボラだからこそ簡単にスケジュールを教えたいと思ったときは単純に「当日~明日」の予定が分かるようにホワイトボードに書くことでした。
ひらがなで予定(行く場所)を書いて、そこに写真を貼っていました。
絵カードも物によっては使えますが、私の場合は買い物や保育園などは、実物の写真の方が伝わりやすいと思ったのでそういったところの情報は写真で伝えるようにしていました。
写真も小さめにコピー、ラミネートして裏にマグネットを付けたりすると可愛くなりますよ🍀
やはり、視覚から入る情報は理解しやすいみたいで落ち着きやすかったです。
③ 落ち着いた後に短く肯定的に伝える
- 長い説教はNG → 「よく落ち着けたね」「また一緒に頑張ろう」で終える
癇癪を起されると、落ち着いたタイミングでなぜ癇癪を起したのか聞いたり、暴れたりするのはダメなことなんだと説明したくなりますが、まだ幼かったり知的障害があると、どんな言葉を投げかけても本人には響きませんし、ストレスにもなります。
癇癪を起した後は、短い言葉で肯定的な言葉をかけるだけで充分です。
叱ること、しつけることも大事ですが、発達障害のある子には理屈が通りません。
常に寄り添い、信頼関係を築くことが長い目で見ても必要不可欠な事だと思います。 - 繰り返すことで子どもも学習していった
発達障害だと、同じような状況で何度も何度もパニックになりますが、本人も日々成長するもので、徐々に癇癪の頻度や度合いは落ち着いていきました。
落ち着いた後の短い肯定的なやり取りがよかったのだろうなと思っています。
やってみて効果が薄かった方法(失敗談)
- 強い声かけ(余計にヒートアップ)
家でも泣いて暴れる姿を見ているのは疲れるので早く終わってほしくなります。
でも感情的になって強く声をかけてしまったときは余計にヒートアップして手が付けられない状態になることがよくありました。
パニックになっている子供に、自分まで熱くなってしまった時にはもう悪循環が止まりません。
強い声かけをしてよかったと思うことは、ほぼありませんでした。 - 無理やり切り替え(外出先で余計に大騒ぎ)
外出先でパニックになってしまった時は、周囲への迷惑も考えるし、視線の恥ずかしさから子供の感情度返しで別のことに意識を向けさせようとして、返って大騒ぎになることもありました。
でもパニックの最中にこちらの言うことを聞く余裕などないのです。
外出先で癇癪が始まったら、何もせずに一旦その場から離れる。
これも失敗から学んだ対応のひとつでした。
まとめ
- 癇癪は「親が悪い」「子どもがわがまま」ではなく、特性による反応
我が子は二人ともよく癇癪を起こして泣いて暴れたいました。
知的障害グレーゾーンの子に関しては、障害とワガママの境界線も分からず
自分の育て方が悪いのか?それとも障害の特性なのか?とかなり悩みました。
でも育てにくさ、普通に暮らしているだけなのに日常生活に支障がある場合は、発達障害の特性から来ているものだと確信しています。
今、発達障害の育児に悩んでいる方がいるとしたら、自分を責めないでほしいです。 - 「見守る・視覚支援・短い肯定的声かけ」で少しずつ改善
正直、癇癪が始まったらもう本人が消化できるまで、見守る以外ない気がします。
落ち着いてきたときに子供からこちらへのアクションがあった時には、短い言葉で肯定的な声かけをして、その繰り返しで本人も少しずつ学び、改善されていきます。
パニックになることが予想される時には、絵カードや写真を使って前もって伝えておくことで落ち着きやすくなることがあるのと、これも繰り返すことで学んでいくのでやってみることをおすすめします。 - すぐにうまくいかなくても「対応の引き出しを増やすこと」が大事
発達障害は治ることはありませんし、今日うまくできたことが明日はできないなんてことは当たり前にありますよね。
我が家ではこの3が効果的でしたが、子どもによって合う・合わないがあります。
対応の引き出しを増やしておくことで臨機応変に動けるようにもなります。
発達障害児の育児は、途方に暮れる場面がたくさん。
けれど、子どもは確実に自分のペースで成長しています。
そんな私もまだまだ成長中ですが(笑)
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が読者様の何かしらのヒントになり少しでもお役に立てたら幸いです。


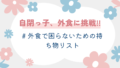
コメント